
スマート農業とは?普及する上での課題や取り組み事例について解説!

オフィスや施設のセキュリティ対策、あるいは業務効率化の一環として、スマートロックを導入する企業が急増しています。従来の物理的な鍵に代わり、スマートフォンやICカード、暗証番号などで施錠・解錠ができるスマートロックは、入退室の記録や遠隔管理にも対応しており、セキュリティ面・管理面ともに優れた機能を備えています。
本記事では、法人がスマートロックを導入する際に押さえておきたい「種類」や「解錠方式」、「設置方法」などの基本知識から、耐用年数やサポート体制といった導入後の運用に関する重要な視点までを、実際の活用事例を交えてわかりやすく解説します。

スマートロックは、出入口の施錠・解錠時に従来の物理的な鍵を使用せず、スマートフォンなどのデバイスを近付けることによって、開閉を行うという新しいシステムです。
スマートフォンなどからの通信で自動的にドアの開け閉めができるようになり、鍵を持ち歩く必要がなくなります。ドア側の鍵部分にも専用の通信機器を設置し、スマホからの通信を受信して、開閉作業を自動で行うという仕組みです。スマートロックにはオートロックの機能もセットで付帯されていることが多く、施錠を忘れてしまう事態を減らせます。
単に鍵の開閉だけではなく、管理・セキュリティ面でも有効なシステムです。データの送受信を行うため「誰がいつ出入りしたか」を詳細に記録することができます。

スマートロックは、単に鍵を「スマート化」するだけではなく、法人の課題解決にもつながる多くの利点を備えたシステムです。近年ではセキュリティ強化や業務効率化、利便性向上といった目的で、企業や公共施設、店舗などさまざまな現場で活用が進んでいます。
ここでは、スマートロック導入における主なメリットとして「セキュリティの強化」「利便性の向上」「業務効率化」という3つの観点から詳しく解説します。
「自社の従業員が不正を働く」というリスクは、残念ながら存在します。スマートロックは従業員が各所へ出入りするに当たり、誰がいつどこに出入りしたかを記録してくれます。不正の発生に対して牽制する効果があり、実際に不正が発生してしまった場合も該当者の探索が容易になります。
一時的な来客や清掃員等にも、スマートロックでの管理を行うことによって、出入り可能な範囲や時間帯を制限することができ、無用な場所への侵入を防ぐことができます。
また、オートロック機能によって、施錠漏れを防ぐ効果もあります。万が一施錠漏れがあった場合でも遠隔地から施錠状況を把握し、遠隔操作で施錠することも可能です。
オフィス向けスマートロックなら、物理鍵を使わずに入退室を行えるのがメリットです。物理鍵は複数の従業員が使っているうちに紛失したり、退職した社員から回収できなかったりといったリスクが伴います。
一方で、スマートロックなら社員証(ICカード)やスマートフォンを使って認証できます。万が一、認証に使うICカードやスマートフォンを紛失しても無効化できるため、物理鍵よりも安全に管理できます。
また、優れた入退室管理機能のあるスマートロックなら、誰にどの部屋へ入退室権限を付与しているかを可視化しやすいのも特長のひとつ。鍵の管理が容易になるため、「紛失リスクや回収の手間が抑えられる」「入退室権限を管理しやすい」などのメリットがあります。
加えて、近年ニーズが高まっている置き配への対応も、スマートロックの活用で実現可能です。宅配業者や委託スタッフに一時的な入室権限を付与すれば、オフィスが無人の時間帯でも荷物を安全に受け取ることができます。再配達の手間を省き、業務効率の向上にもつながります。
従来からの「タイムカード」による勤怠状況の管理では、打刻漏れや不正等が発生するリスクがあります。
スマートロックの導入によって、職場への入室時間と退室時間が記録されるため、勤怠管理システムとの連携により、自動的に勤怠状況の把握が可能となります。
出退勤時だけではなく、特定の従業員が今どこにいるかも把握しやすいため、就業時間中の行動管理を行うこともできます。

スマートロックは「鍵のない生活」を可能にするだけでなく、業務効率化や人件費の削減、顧客満足度の向上にもつながるソリューションとして、さまざまなシーンで導入が進んでいます。ここでは、実際に活用されている代表的な3つの分野を紹介します。
スマートロックは、賃貸住宅における「内見」や「内覧」の効率化に役立ちます。不動産営業が同行しなくても、スマートフォンでデジタルキーを発行することで、鍵の受け渡しなしに自由に物件を見学できるようになりました。
また、入居手続き後もスマートフォンアプリで鍵を受け取るだけで、入居日からすぐに新生活をスタートできます。契約・入居までの流れがスムーズになることで、借主・貸主双方にメリットがあります。
無人店舗では、スタッフが常駐せずとも24時間営業を可能にするために、スマートロックが欠かせません。利用者はスマートフォンアプリや暗証番号を使って自由に店舗を出入りできるため、スタッフを配置せずに済み、大幅な人件費削減につながります。
深夜営業や混雑時間帯を避けた利用など、顧客の利便性を高めながら、運営側のコストも削減できる点が大きな魅力です。
宿泊施設では、チェックインやチェックアウトを無人化する手段としてスマートロックの導入が進んでいます。予約システムと連携することで、ゲストごとに異なる暗証番号を自動発行し、フロント業務を最小限に抑えることができます。
スタッフを常駐させずに運営できるため、人件費を削減できるだけでなく、深夜や早朝のチェックインにも対応可能です。
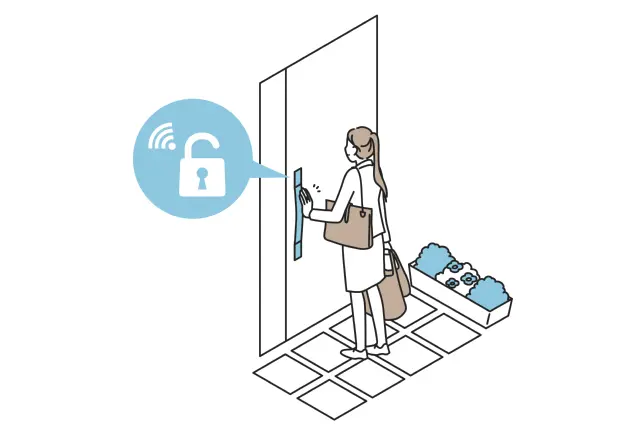
スマートロックは、セキュリティ性の向上だけでなく、勤怠管理や施設管理の効率化にも大きく貢献する便利なシステムです。しかし、商品ごとに機能や仕様が異なるため、目的に合ったものを選ばなければ十分な効果は期待できません。
ここでは、スマートロックを選ぶ際に重要となる「機器の設置方法」「認証方式」「耐用年数」「サポート体制」という4つの観点から、最適な選び方を解説します。
スマートロックには大きく分けて、後付け型、シリンダー交換型、穴あけ工事型の3種類の設置方法があります。
賃貸住宅やオフィスなど、ドアを加工できない物件に向いているのが後付け型です。既存のドアに両面テープなどで取り付けるだけで簡単に設置でき、退去時には原状回復も可能という手軽さが魅力です。ただし、経年劣化や外部からの衝撃に弱いため、耐久性の面ではやや不安が残ります。
一方、長期間の利用を前提とする戸建て住宅や企業のオフィスには、シリンダー交換型や穴あけ工事型のスマートロックが適しています。これらはより頑丈で、外れにくく、セキュリティ性も高いというメリットがあります。特に穴あけ工事型は、施設全体の安全を重視する商業施設や新築住宅に最適です。
スマートロックの選び方において、どのような方法で解錠するかが重要です。解錠方式には、スマートフォン、ICカード、暗証番号、生体認証などさまざまな種類があり、それぞれに向いているシーンが異なります。
個人住宅や社員数の少ないオフィスでは、スマートフォンアプリによる解錠が主流です。所有者本人のスマホが鍵代わりになるため、物理的な鍵の管理が不要となり、紛失リスクを大きく軽減できます。また、荷物を持ったままでの出入りが多い場合は、スマートフォンをドアに近づけるだけで自動的に解錠される「ハンズフリー解錠」が便利です。
一方で、不特定多数が出入りする施設や無人店舗のようなシーンでは、暗証番号による解錠が好まれます。利用者がデバイスを持っていなくても操作できるため、利便性が高い反面、番号の漏洩リスクがある点には注意が必要です。セキュリティをより重視する場合は、指紋や顔などを使った生体認証方式を選ぶのが安心です。
施設の特性や利用者の傾向をしっかりと見極めた上で、最も適した認証方式を選ぶことが、快適で安全な運用につながります。
スマートロックは電子機器である以上、耐用年数やメンテナンス頻度も製品選びの重要な指標となります。特に安価なモデルや後付け型タイプは、3〜5年程度で買い替えが必要になることも多く、長期的に使用する場合は初期費用よりもトータルコストを考慮して選ぶ必要があります。
シリンダー交換型や工事型のスマートロックは、10年以上の耐久性を想定して作られている製品も多く、安定性を求める施設には適しています。加えて、どのようなデバイスを利用するかによってもコストは変わります。既存の社員証などのICカードをそのまま活用できるシステムであれば、追加費用を抑えることができ、スマートフォン連携であれば個別の機器購入も不要です。
一方、生体認証システムは高いセキュリティを誇る反面、導入コストが高くなる傾向にあるため、用途に応じて慎重に選定しましょう。
どれほど高性能なスマートロックであっても、ネットワーク障害や機器の不具合、設定ミスなどによって突然使えなくなるリスクはゼロではありません。そのため、導入前に必ず確認しておきたいのがサポート体制の内容です。
万が一のトラブル時に、迅速かつ確実に対応してもらえる体制が整っているメーカーであれば、安心して導入・運用が可能です。特に法人や公共施設では、24時間体制のカスタマーサポートがあるか、電話・メール・チャットなど連絡手段が豊富か、緊急時の現地対応が可能かといった視点が重要です。
また、サポートの内容や対応スピードだけでなく、初期設定時のフォローや操作説明の有無、導入後のメンテナンス体制まで含めて総合的に判断しましょう。
日本全国をカバーする施工・保守体制を有するバディネットでは、IoT・ロボット・EV充電設備・クラウドカメラなどの先端技術に関わる工事や、オフィスビル・学校・病院・商業施設などさまざまな建物における電気設備の設計・施工をはじめ、EV充電設備や太陽光発電設備、蓄電池等の電気工事を手掛けています。専有部、共有部ともに、スマートロック設置工事のご要望にも対応可能です。
ICカード、暗証番号、スマートフォン、生体認証などの認証方式やBluetooth、Wi-Fi、NFCといった通信方法を考慮し、最適な設置方法をご提案いたします。
また、通信状況の確認やトラブルシューティングやソフトウェアのアップデートや、故障時の修理、コンタクトセンターを導入後のカスタマーサポートなどのアフターサポートについてもご支援いたします。
スマートロックは、単に鍵の代替として便利なツールというだけでなく、企業のセキュリティ強化や業務の効率化、コスト削減や無人化の推進にもつながる有用なシステムです。法人での導入においては、製品の機能面だけでなく、設置環境への適合性や運用コスト、トラブル時のサポート体制など、複数の視点から慎重に検討することが不可欠です。
これからスマートロックの導入を検討されている企業の方は、本記事で紹介したポイントを参考に、自社にとって最適なデバイスを選択しましょう。
この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部
Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。