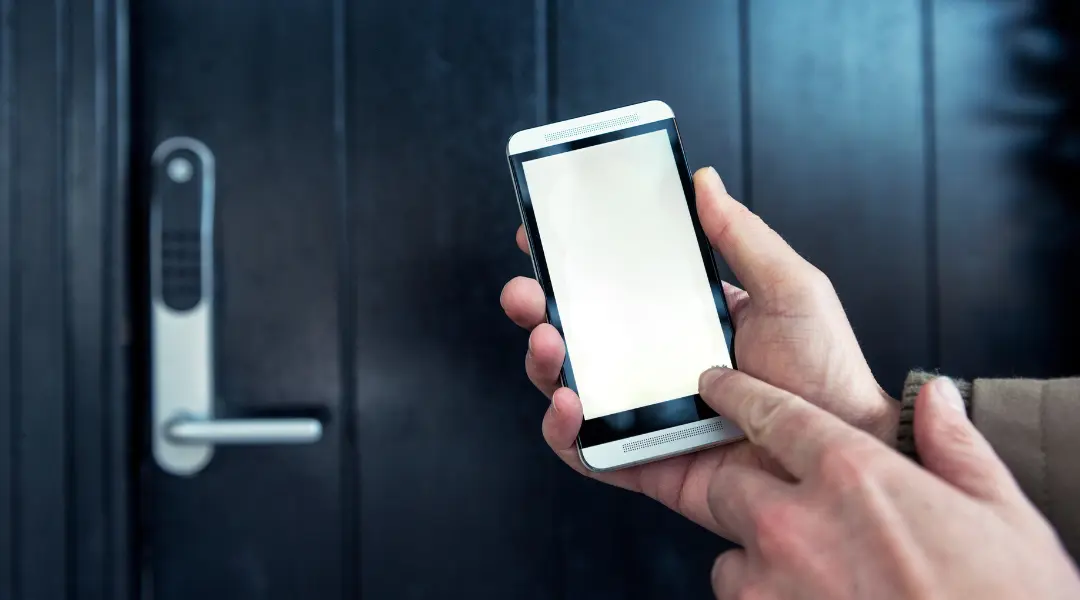
【法人向け】失敗しないスマートロックの選び方とは?種類・機能から設置・保守の注意点まで解説

スマート農業は、ICT・IoT・AIなどの先端技術を農業に導入し、生産の効率化や品質向上を実現する新しい農業の形です。人手不足や高齢化といった課題を解決するためのものであり、ドローンや自動運転トラクター、AIによる生育分析など、現場を支える技術が次々と実用化されています。
本記事では、スマート農業の仕組みや導入によるメリット、普及を妨げる課題、全国で行われている取り組み事例をわかりやすく解説します。

スマート農業とは、農業の現場にICT(情報通信技術)やIoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)などの最先端技術を導入し、生産の効率化や品質向上を図る新しい農業の形を指します。これまで人の経験や勘に頼ってきた作業を、データ分析や自動制御によって最適化することで、省力化・高収益化・持続可能な農業の実現を目指す取り組みです。
この概念が本格的に注目され始めたのは、2013年に農林水産省が「スマート農業の実現に向けた研究会」を立ち上げた頃からです。当時から少子高齢化による労働力不足が課題となっており、テクノロジーを活用して省人化・自動化を進める必要性が高まっていました。つまり、スマート農業は近年始まった新しい取り組みではなく、10年以上前から国を挙げて推進されてきた施策です。
その目的の中心にあるのは、深刻化する担い手不足の解消です。ドローンや自動走行トラクター、センサー付き水管理システムなどを導入することで、人手に頼らず効率的な農作業が可能となり、高齢者や女性、未経験者でも参入しやすい環境が整います。さらに、データに基づく精密な栽培管理により、品質の安定化や収量の向上も期待されています。
また、2019年度には農林水産省による「スマート農業実証プロジェクト」が始動しました。全国の実証地区で最新技術を導入し、その効果を検証する取り組みであり、導入による省力化・コスト削減・収益向上の成果が続々と報告されています。

スマート農業に用いられる技術は、従来の経験や勘に頼る作業をデータ化・自動化し、農業の効率と精度を飛躍的に高めています。特にドローン、センサー、AI、ロボットの4つは、現場の課題を解決する主要な技術として注目されています。
ドローンは、これまで人の目で確認していた圃場(ほじょう)の状態を、空から俯瞰的に把握できる画期的なツールです。上空からの撮影データを解析することで、作物の生育ムラや病害虫の発生、雑草の繁茂状況を高精度に把握できます。広大な圃場でも短時間で状況を把握でき、農薬散布などの作業を効率化できる点が大きな強みです。かつて時間と労力を要していた「見回り作業」は、ドローンによってデジタルデータとして蓄積・分析できる時代へと進化しました。
センサー技術は、気象条件や土壌環境をリアルタイムで把握するための重要な手段です。気象センサーでは、気温・湿度・降水量・風速などの局所的データを収集し、天候の急変に対して迅速な対応を可能にします。
土壌水分センサーでは、地中の水分量や電気伝導度、地温などを測定し、適切な潅水や施肥の判断に役立ちます。これらのデータを活用すれば、勘や経験に頼らずに科学的な根拠に基づいた農業が実現し、作業の省力化と品質向上の両立が可能になります。
AI(人工知能)は、センサーやドローンが集めたデータを解析し、農作業の最適化を支援します。画像認識技術によって作物の病害を早期に検出したり、過去の気象データと照らし合わせて収穫量や最適な収穫時期を予測したりすることができます。
AIは利用を重ねることで学習精度が向上し、より精緻な判断が可能になるため、長期的に活用することで生産性と品質の向上に直結します。
農業用ロボットの進化もスマート農業の大きな柱です。除草ロボットはカメラやセンサーを使って雑草を判別し、自動で取り除くことで労働負担を軽減します。収穫ロボットは作物の熟度を判定して最適なタイミングで収穫を行い、人の判断に依存していた繊細な工程を正確にこなします。
こうしたロボットの導入により、肉体的負担の軽減と安定した品質の両立が実現し、農業はより持続可能で魅力的な産業へと変わりつつあります。

スマート農業の導入は、単なる作業の自動化にとどまらず、農業の在り方そのものを大きく変える可能性を秘めています。技術の活用によって生産性を高めるだけでなく、品質向上、コスト削減、技術継承といった多方面でのメリットが得られます。
農業は気候条件や病害虫、土壌環境など、さまざまな要因が収量や品質に影響を与えます。スマート農業では、気象データや生育情報をセンサーやドローンで収集・解析し、最適な栽培環境を科学的に導き出すことが可能です。
従来の「経験と勘」に頼った判断から、データに基づく精密な栽培管理へと進化することで、病害の発生を未然に防ぎ、均質で高品質な作物を安定的に生産できるようになります。その結果、ブランド価値の向上や市場競争力の強化、さらには収益性の改善にもつながります。
農業の現場では、労働力不足と人件費の高騰が大きな課題です。自動運転トラクターや収穫ロボット、ドローン散布システムなどを導入することで、作業の効率化と人手削減を両立できます。
完全自動化が難しい場合でも、スマートフォンやタブレットからの遠隔操作によって半自動的に作業を進めることができ、天候や時間に左右されにくい柔軟な農業経営が可能になります。さらに、AIが生育データをもとに判断し、ロボットが実作業を行う体制を構築すれば、現場の負担を大幅に軽減しながら安定した生産体制を維持できます。
日本の農業では高齢化が進み、熟練農家の技術や経験を次世代に引き継ぐことが困難になっています。スマート農業では、ベテラン農家が長年培ってきた栽培方法や判断基準をデータとして蓄積・共有できるため、知識の属人化を防ぎ、若手や新規就農者でも高度な技術を活用した農業を実践できるようになります。
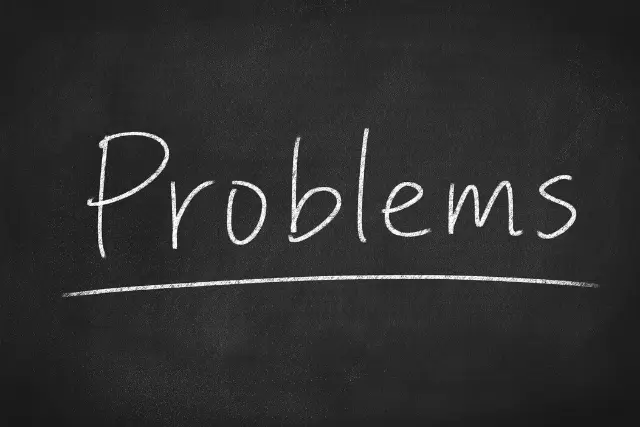
日本におけるスマート農業の導入は年々進展しており、一定の成果を上げつつも、地域や業種によって普及度に差が見られます。
日本政策金融公庫の「農業景況調査(令和7年1月)」によると、スマート農業をすでに導入している農業者の割合は全体で44.9%に達しました。およそ半数近くの農業経営体が、何らかの形でスマート技術を活用していることになります。
導入率を分野別に見ると、耕種分野では畑作が最も高く68.7%、稲作では北海道が55.4%、都府県では49.2%と比較的高い数値を示しています。畜産分野では酪農が北海道で43.8%、都府県で43.2%と、全国的に導入が進んでいることが明らかになりました。これらの結果から、広大な圃場を持つ地域や、機械化・自動化が労力軽減に直結する分野ほど、スマート農業の活用が進んでいる傾向がうかがえます。
【記載内容】
「日本政策金融公庫の調査(2025年3月)によると、スマート農業の導入状況は44.9%」
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「スマート農業は44.9%が導入済み、稲作(北海道)や畑作では半数超え ~ 導入に際しての課題は「初期投資費用が高い」が約8割 ~」(日本政策金融公庫)を参照し、作成
自動運転トラクターや収穫ロボット、ドローン、環境制御システムなど、スマート農業を支える機器は高度な技術を要するため、どうしても価格が高額になります。特に中小規模の農家にとっては、数百万円単位の投資を短期間で回収するのは難しく、導入に踏み切れない要因となっています。結果として、一部の大規模経営体や企業参入農場を中心に普及が進み、小規模農家が取り残される構図が生まれつつあります。
今後は、国や自治体による補助金制度の拡充、機器メーカーのリース・サブスクリプション化、共同利用モデルの普及など、初期負担を軽減する仕組みづくりが重要となるでしょう。
日本の農業従事者の多くは高齢化が進んでおり、長年の経験と勘に基づいた栽培スタイルが根付いています。そのため、データ分析やアプリ操作など、デジタル技術に基づく管理方法に慣れるまで時間がかかることも少なくありません。スマート農業の本格的な普及には、単に機器を導入するだけでなく、それを使いこなせる人材の育成とサポート体制の構築が不可欠です。
農業高校や大学、行政機関、メーカーが連携して教育・研修プログラムを提供するほか、農家と技術ベンダーの間をつなぐデジタル支援人材の育成も求められています。
スマート農業では、センサーやロボット、クラウドシステムを常時ネットワークで接続し、リアルタイムにデータを送受信する必要があります。しかし、農地は山間部や平野部の奥地に位置することが多く、安定した通信環境を確保するのが難しいのが現実です。
全国各地で進むスマート農業の導入は、地域の特産品や気候条件に合わせて多様な形で展開されています。ここでは、実際の取り組みの中から注目すべき事例を紹介します。
秋田県羽後町は、県内でも有数のトルコギキョウの産地として知られており、毎年6月から11月にかけて首都圏を中心に安定した出荷が行われています。トルコギキョウは生育段階ごとに適切な水分量や施肥の管理が求められる繊細な花であり、特に大規模な団地栽培では管理作業に多くの労力が必要とされています。
こうした課題を解消するため、ICT技術を活用した生産環境の自動管理に取り組んでいます。圃場に環境モニタリング機材を設置し、温度・湿度・土壌水分などのデータをリアルタイムで把握できる体制を整えました。さらに、自動潅水装置を導入することで、収集したデータに基づき植物の生育に最適なタイミングで水や養分を供給できるようになっています。これにより、潅水労力を約62%削減できるなど、作業の省力化と管理の精度向上が実現し、再現性の高い安定した花き生産を目指す取り組みが進められています。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「令和3年度次世代につなぐ営農体系確立支援事業 雄勝園芸ICT協議会(秋田県羽後町)」(農林水産省)を参照し作成
岐阜県郡上市高鷲町にある「ひるがの高原だいこん生産出荷組合」は、生産者22名、栽培面積77ヘクタールを誇る大規模な産地であり、令和2年産では約4億7千万円の販売実績を上げています。令和元年度までは外国人技能実習生を中心に労働力を確保していましたが、新型コロナウイルスの影響により、観光業など地元産業からの労働者を新たに雇用する方針へと転換しました。
その一方で、作業の機械化を積極的に進めた結果、農家1戸あたりの経営規模が拡大し、雇用労力への依存度も高まっています。しかし、新たに雇用された作業者は圃場の形状や傾斜、土質の違いに慣れる必要があり、機械操作や生育管理の技術を習得するまでに時間がかかるという課題がありました。
この課題を解決するため、組合ではスマート農業機械の導入を進めています。自動運転トラクターや自動操舵乗用管理機を導入することで、経験の浅い作業者でも正確な作業ができる環境を整えました。実証結果では、耕起・畝立て・防除といった主要作業において、熟練者とほぼ同等の作業精度と作業効率が確認されています。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「令和3年度次世代につなぐ営農体系確立支援事業 ひるがの高原だいこんスマート農業研究会(岐阜県郡上市)」(農林水産省)を参照し作成
株式会社バディネットは、IoT/5G時代のインフラパートナーとして通建テック®事業を展開しており、このたび株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)が実施する「令和5年度 愛媛県デジタル実装加速化プロジェクト(トライアングルエヒメ)」のスマート農業実装事業に参画しました。
本プロジェクトでは、温州みかんの主要産地である愛媛県・真穴柑橘共同選果部会(真穴共選)のみかん畑約240ヘクタールを対象に、IoTネットワーク「LoRaWAN®」の構築と運用を行っています。
バディネットは、IIJと連携し、LoRaWAN®ネットワークの調査・設計・施工を担当。さらに、みかん畑全体に土壌センサーや気象センサー、獣害対策用の罠センサーなどを設置する基地局の構築を実施しました。LoRaWAN®は低消費電力かつ長距離通信が可能なLPWA技術で、広範囲の農地を効率的にカバーできる点が特徴です。
このネットワークを通じて収集された土壌水分データはクラウド上で分析・可視化され、最適な栽培モデルの構築に活用されます。データに基づきスプリンクラー灌水を自動制御することで、過乾燥や落葉を防ぎ、収穫減のリスクを低減します。

バディネットは、人手不足や高齢化が進む農業分野のスマート化を、プロジェクトの計画段階から支援しています。デバイスの開発・調達からインフラ構築、デバイス設置工事、保守までをワンストップで担っています。
スマート農業の基盤となる通信インフラの整備は、バディネットの得意分野です。電気通信工事で培った豊富なノウハウを活かし、広大な圃場(田畑)をカバーするLPWA、温室内のWi-Fi、大容量データ伝送に対応する5G/ローカル5Gなど、多様な通信環境を構築します。
また、AKIBAホールディングスグループであり、IoT機器の設計・開発・製造をワンストップで提供するアドテック社と連携。課題解決に最適な専用センサーやデバイスの開発・調達から設置工事まで、トータルソリューションの提供が可能となります。
さらに、専門のエンジニアが農家と直接対話し、山間部や沿岸部といった特殊な環境でも、地形や土質を考慮した最適な工法を設計・提案します。日本全国をカバーする施工・保守体制を活かし、デジタル技術の導入から地域への定着までを強力に後押しいたします。
スマート農業は、テクノロジーの力で日本の農業を持続可能な形へと進化させる重要な取り組みです。AIやIoTを活用した精密農業は、品質向上や収量安定化に貢献するだけでなく、労働力不足の解消にもつながります。
一方で、導入コストやITリテラシー、通信環境といった課題も残されています。今後は補助制度や教育体制の整備、地域に合った実証事例の共有が普及の鍵となるでしょう。
この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部
Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。