
清掃ロボットを導入するメリットや選ぶ際のポイントについて解説!

サービスロボットの導入を検討しているものの、具体的にどのように活用できるのか、費用対効果がどの程度あるのか判断しかねて悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、サービスロボットの定義やおもな種類、導入事例や導入にあたっての課題などを解説します。
サービスロボットは日々進化しており、うまく使いこなせれば省人・省エネ化や業務効率化に威力を発揮します。本記事では導入事例も紹介しているので、導入をお悩みの方はぜひ参考にしてください。

サービスロボットとは、人間の生活や業務をサポートすることを目的として設計されたロボットの総称です。小売業や各種サービス業で使用されることが多く、受付や案内、荷物の運搬、掃除、介護などさまざまなシーンで活用されています。飲食店で働く配膳ロボットや、商業施設で掃除する清掃ロボットを見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
業務の効率化や省人化・省力化による人手不足解消など、企業が抱える課題を解決する手段として注目されています。
ロボットは、大きく以下の2つに分類できます。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 産業用ロボット | ● おもに工場で用いられ、製造現場で人に代わって作業を担う機械装置全般を指す ● 組立、塗装、溶接などの作業を高精度でおこなう |
| サービスロボット | ● 産業用ロボット以外のロボット全般を指す ● 人間の生活やサービスにかかわり、人がおこなう作業の補助を担う ● 非定型業務を担うこともできる |
両者の大きな違いは、活用される場所にあります。産業用ロボットは製造業の工場などで産業の自動化を目的として使用される機械装置です。それ以外の場所で活用されるロボットは、すべてサービスロボットとして扱われます。
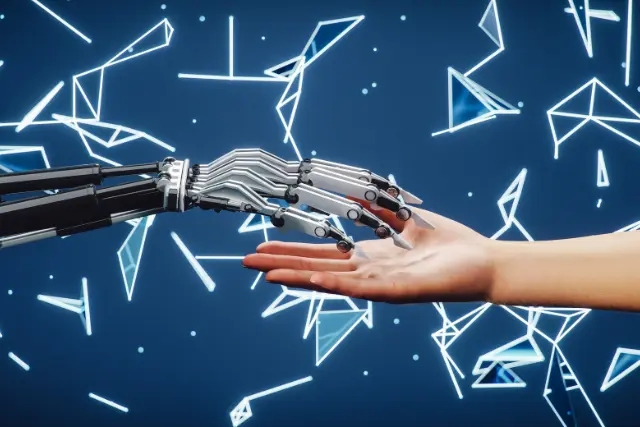
サービスロボットは、屋内用と屋外用に大別でき、それぞれ以下のような場所で活躍します。
ここでは、代表的なサービスロボットの種類や活用シーンを紹介します。
飲食店や病院、ホテル、オフィスなどで料理や荷物を自動で運ぶロボットです。製品により異なりますが、おもに以下のような機能があります。
飲食店では注文の受付から配膳・下げ膳まで可能です。ホテルやオフィスではお客様の荷物や備品、書類などを指定の場所に届けます。
現場での人手不足を解消する有効な手段として需要が高まっており、人件費削減や作業効率の向上などのメリットがあります。
ホテルやオフィス、商業施設、空港などで床掃除やカーペット清掃、ガラス拭きなどの掃除を担うロボットです。製品にもよりますが、代表的な機能に以下があります。
プログラムされたルートにそってムラなく掃除するため、高い水準の清掃品質を保持できる点が大きなメリットです。従業員が清掃に時間を割かなくてよくなり、コア業務に集中できるようになることで、生産性の向上も見込めます。
清掃ロボットを導入するメリットや選ぶ際のポイントについて解説!
企業や商業施設などの受付で、来訪者対応をおこなうロボットです。代表的な機能に以下があります。
受付や案内用の人員を削減できるだけでなく、来客対応の標準化が図れ、一定の品質を保持できるようになります。また、多言語に対応でき、外国からのお客様をスムーズに受付・案内できる点もメリットです。ロボットが受付業務をおこなう先進性もアピールでき、ブランディング効果も期待できるでしょう。
オフィスビルや工場、公共施設などで巡回や監視等の警備や防護をおこない、事故や盗難などに対応するロボットです。巡回型、ドローン巡回型、遠隔操作型などの種類があります。
代表的な機能は以下の通りです。
24時間365日警備できる点が大きな強みです。人手不足でも終日の監視体制を無理なく構築でき、犯罪リスクに迅速に対応できます。人の目では察知できない異常を検知できるなど、より精密な警備も期待できるでしょう。
病院や介護施設において、医療や介護のサポートをおこなうロボットです。
医療ロボットは、おもに以下のようなシーンで活躍します。
介護ロボットのおもな機能は以下の通りです。
医療従事者や介護者の負担軽減につながるだけでなく、高齢者の自立支援にもつながる点が大きなメリットです。
農薬散布や草刈り、収穫など農業に必要なさまざまな業務を担うのが農業用ロボットです。トラクター型ロボットやドローン、アシストスーツなど多種多様なものがあり、以下のような作業を実施・支援します。
作業を省力化でき、生産性の向上が見込める点が大きなメリットです。
地震や洪水などの災害が発生した際に、危険が伴う地域で行方不明者の捜索や情報収集をおこなうロボットです。レスキューロボットとも呼ばれます。
ドローンや小動物を模した小型ロボット、人型などさまざまなタイプがあり、種類によって以下のような作業が可能です。
災害現場の二次災害防止や被災状況の迅速な把握に役立つ点がメリットです。救助活動を効率化し、安全確保に大きく貢献します。
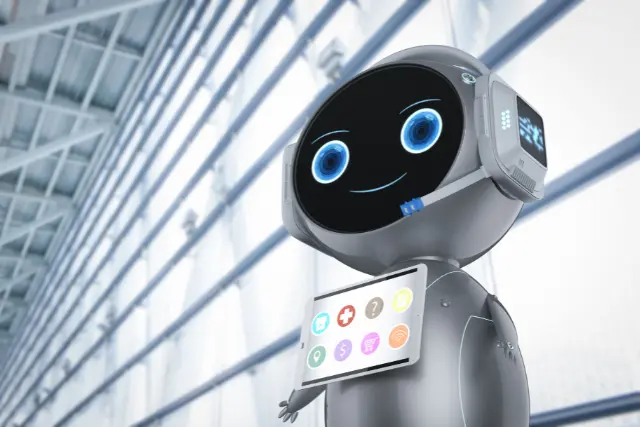
サービスロボットの種類については分かっても、実際に導入してどのように役立つかピンとこない方も多いのではないでしょうか。そこで、ここでは実際の導入事例をいくつか解説します。
実際の導入・運用例やその効果を知り、導入にあたっての参考にしてください。
神奈川県藤沢市のスマートタウン「FujisawaSST」では、野菜・パンなどの地域食材・食品をオンラインで販売しています。その配送方法において、ロボットでの配送サービスを実施しました。住宅街を4台のロボットが走行し、東西約700m・南北約500mのスマートタウン内で商品を自宅まで送り届けています。
導入後、地域住民からは「湘南ハコボ」という愛称がつけられ、ロボットがより町に溶け込めるような仕掛けも行われています。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、経済産業省(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構「自動配送ロボット活用の手引き:第4章自動配送ロボットの活用事例集」を参照し、作成
富士川町役場では人手不足対策と生産性向上を目的とし、AI案内ロボットTimoを導入・運用する実証実験を行いました。当役場が抱えていた具体的な課題とは、総合窓口がなく、入口に近い課の職員が案内業務も担っているため負担が大きく、通常業務の効率が落ちるというものです。
Timoは人や障害物を避けながらの自動走行が可能で、来庁者が用件を伝えると対応窓口を音声で伝えて目的地まで先導して案内いたします。案内業務をロボットが代替することで、職員の負担軽減につながりました。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、富士川町「令和6年6月 町長日記」、公民連携推進機構「自治体の人手不足」解決提案として山梨県富士川町にて「AI案内ロボット」導入」を参照し、作成
神奈川県にある商業施設「横浜四季の森フォレオ」では、施設内の清掃業務の効率化や遠隔警備の必要性、案内業務の拡充といった課題を抱えていました。そこで、課題解決のために行ったのが、ロボット実装促進事業を利用した清掃・警備・案内の3機能を有する複合型サービスロボットの導入です。
ロボットの導入により特に明確な効果が見られたのは、清掃業務です。1日あたり13.5時間分の清掃業務工数の削減を実現できることが確認されました。警備、案内業務においても一定の効果、貢献があったと推察されています。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、神奈川県 ロボット実装促進センター「case02 横浜四季の森フォレオ」を参照し、作成
社会福祉法人京都太陽の園では、京都府が実施するロボット導入支援事業を利用して、据置型介護リフトを導入しました。工事や固定不要のポータブルリフトで、介護が必要な方の移乗介助がスムーズに行えます。
導入した結果、利用者の方の移乗介助に必要な人員を2人から1人に削減できました。2人必要だったときは他の支援員を探しに行くために発生していた利用者の待ち時間も短縮されています。また、職員の身体負担も軽減でき、腰痛予防にもつながりました。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、京都府「障害福祉分野のロボット等導入支援事業導入事例 令和5年度障害福祉分野のICT導入モデル事業」を参照し、作成

サービスロボットは導入メリットが多く、今後も普及が見込まれる一方、いくつかの課題も存在します。
とくに、以下のような課題が挙げられます。
サービスロボットの導入においてもっともネックとなることの一つが、導入コストの高さです。導入時に発生するのは、サービスロボット本体の料金だけではありません。ロボットの種類にもよりますが、ほかにも周辺設備の整備やソフトウェアのカスタマイズ、現場スタッフの教育などにコストがかかることが一般的です。
また、サービスロボットは定期的なメンテナンスやアップデートが必要で、導入後にもランニングコストが発生します。トータルコストに見合うだけの効果や利益が得られるか判断することが難しく、導入の壁となっているケースは少なくありません。
導入の目的を明確にし、達成するのに最適なロボットを慎重に見極める必要があります。
導入への課題として、技術的な問題や現場における専門知識を持った人材の不足なども挙げられます。
ここでは、どのような技術的課題があるのか、専門知識の不足とはどういうことかについて解説します。
サービス業の現場では、サービスロボットが予期しない環境や状況が発生することがあります。サービスロボットは搭載されたカメラやセンサーで状況を把握したりAIで適切な行動を判断したりすることはできるものの、サービス業や小売業の現場では柔軟な対応が求められることも多く、常に完璧に対処することは容易ではありません。誤作動が発生する場合もあるでしょう。
複雑な環境でも適切に対応させるためには、現場の状況にもっとも合ったロボットを導入することが必要です。
サービスロボットの多くは、現場の業務システムやインフラと連携する必要があります。とはいえ、ロボットとほかのシステムとの連携は、標準化が進んでいるものの十分とは言いがたく、場合によっては個別開発が必要です。その場合、現場で使えるようになるまでに時間やコストがかかります。また、連携にあたっては十分なセキュリティ対策を講じることも必要です。
社内の人材だけで対応するには技術的なハードルが高く、導入にあたっての課題となります。
自社でサービスロボットを適切に運用し、求める結果を出すためには、AIやシステム管理などに関する専門知識やスキルを持つ人材が必要です。また、トラブルが発生したときにすみやかに対応したり、運用の課題点を改善したりするためには、現場でもある程度のスキルを持ったスタッフが要るでしょう。
しかし、多くの企業でそのような高いスキルや知識を持った人材が足りていないのが現状で、サービスロボット導入の障壁となっています。
サービスロボットの導入にあたっては、法規制や論理的な問題にも注意が必要です。たとえば、人とロボットが接触して事故が発生した場合に責任の所在はどこにあるのか、プライバシー保護の観点からみてロボットが監視したり記録を取ったりすることはどこまで許されるのかなどについて、まだ明快にはなっていません。
法的な枠組が十分に整備されているとは言えず、サービスロボットが介護を担う場合、介護される側の人としての尊厳にどの程度の影響を及ぼすのかなど、倫理面でも問題が残ります。
こうした法的規制や倫理的な問題を残したまま、導入をどこまで進めていいか判断しかねているケースもあるでしょう。
サービスロボットを使用・利用する側がどれだけ受け入れられるかも、導入にあたっての課題の一つです。特に高齢者や機械操作を苦手とする人々は、ロボットを使うことに対して心理的な抵抗感や不安を覚えるケースがあります。たとえ高性能で利便性の高いロボットでも、操作が複雑だと導入しても使われない可能性もあるでしょう。
従業員たちの心理的抵抗を減らし、使用を促進するためには、丁寧に説明し、機械操作に慣れるためのトレーニング期間や慣らし運用期間を設けることが必要です。一般のお客様の利用を想定している場合は、直感的な操作が可能なUIのものを選ぶ必要もあるでしょう。
サービスロボットは、導入さえすれば終わりではありません。導入後は適切な運用を続けながら、定期的なメンテナンスやアップデートを実施する必要があります。不具合が生じれば、速やかな対応が必要です。
運用やサポート体制が十分に整っていなければ、トラブルが発生した際に現場での混乱や業務の停滞を招きかねません。現場によっては深刻な問題に発展する恐れもあるでしょう。
そのため、現場であまり高い知識がなくても簡単に設定・操作できるモデルを選ぶことが必要です。また、導入前から導入後までサポートを受けられるサービス事業者を選ぶことも大切なポイントとなるでしょう。
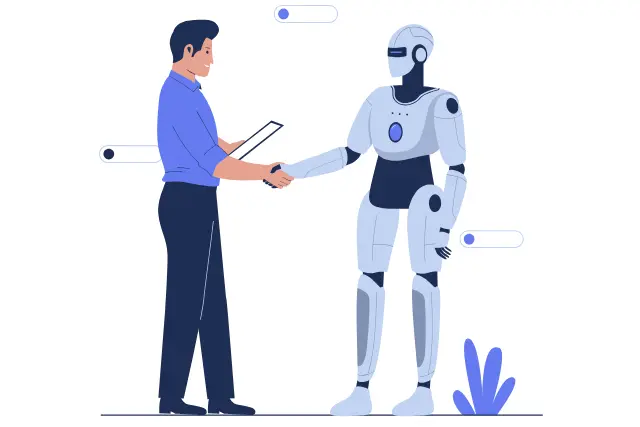
日本全国にサービス拠点を持ち、サービスロボット導入支援業務において業界随一の実績を誇るバディネットには、特定のメーカーや種類のロボットに偏らず、様々なサービスロボット(清掃ロボット、配膳ロボット、案内ロボット、警備ロボットなど)の特性、機能など技術面を熟知しているエンジニアが多数在籍しています。
また、ロボットエンジニア部隊と24時間365日有人対応が可能な全3拠点のコンタクトセンターを連携活用することで、サービスロボット導入において必要となる、現地顧客との折衝、現地調査、設計、導入当日の支援から導入後の定期点検、障害発生時における問い合わせ窓口からオンサイト保守に至るまで、ワンストップでご提案が可能です。
導入ロケーションに関しても、大型商業施設からテナント(コンビニ・飲食店)、ホテル、医療施設やオフィスまで幅広い施工実績がありますので、事業者様の様々な要望に柔軟に対応いたします。
バディネットのサービスロボット設置・保守に関する詳細はこちら
サービスロボットの定義や産業用ロボットとの違い、おもなサービスロボットの種類などについて解説しました。サービスロボットにはさまざまなタイプがあるため、導入にあたっては目的や利用環境にマッチした種類を選ぶことが大切です。適切に運用することで人手不足解消や業務効率化など、企業が抱える課題の解決に大きく貢献するでしょう。
バディネットでは、全国に広がるネットワークを活用し、サービスロボットの導入・運用を徹底的にサポートしています。ぜひご相談ください。
この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部
Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。