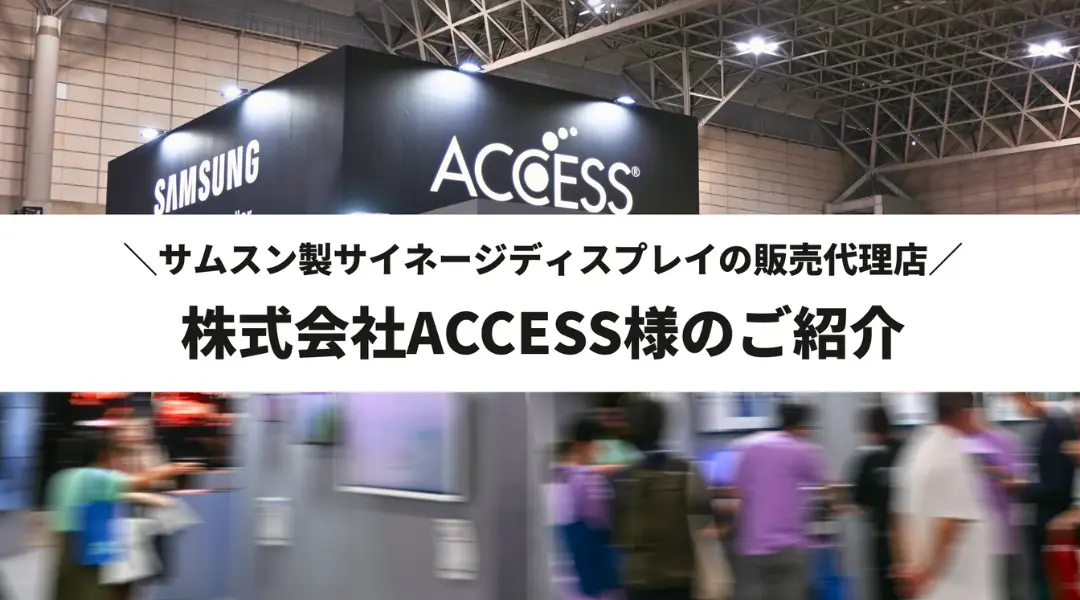
\サムスン製サイネージディスプレイの販売代理店/ACCESS様をご紹介します!

教育現場では、GIGAスクール構想によって1人1台端末の環境整備が進み、ICTを活用した学びが日常化しつつあります。しかし、端末の老朽化や活用格差、教員のICTスキル不足など、次のフェーズ「NEXT GIGA」では新たな課題も浮き彫りになっています。
こうした中、授業の質を高め、協働学習や探究学習を促進する手段として注目されているのが電子黒板です。本記事では、電子黒板の導入メリットや活用事例を紹介するとともに、NEXT GIGA時代の教育における可能性について解説します。

GIGAスクール構想で進んだ1人1台端末環境は、学びの幅を広げましたが、活用格差や機器更新などの課題も残されています。こうした中、電子黒板は授業の質を高め、協働学習や探究的活動を促進する解決策として注目されています。電子黒板が教育現場で必要な理由について詳しく見ていきましょう。
GIGAスクール構想は、全国の学校におけるICT(情報通信技術)環境を飛躍的に充実させ、児童生徒や教員が持つ力を十分に引き出すことを目的とした施策です。文部科学省が2019年に発表し、小学校・中学校・高等学校などを対象に、高速大容量の通信ネットワークを整備するとともに、児童生徒一人ひとりに学習用端末を行き渡らせる取り組みが進められています。
NEXT GIGAは、初期のGIGAスクール構想で築かれたICT教育基盤をさらに進化させるための新たなステージです。これまでの施策によって、全国の学校では高速通信環境と児童生徒一人一台の端末が整備され、学びのデジタル化が一気に加速しました。しかし、その先にある持続的な活用には、いくつかの壁が立ちはだかっています。
最大の課題は、端末の老朽化です。活用が日常化するにつれて故障が増え、バッテリーも耐用年数である4〜5年を迎えつつあります。自治体によっては、2024年度中にも大量更新が必要となる見込みで、予算確保や調達の計画が急がれています。
また、地域や学校ごとの利用度合いの差も無視できません。端末があっても授業で活用できなければ意味がなく、その背景には教員のICTスキル不足、研修機会の限定、支援員の不足といった要因があります。NEXT GIGAでは、こうした人的・環境的な課題を解消し、どの学校でも端末が日常的に活きる教育環境を整えることが求められます。
ここで忘れてはならないのが、世界とのギャップです。日本はGIGAスクール構想によって一気に整備が進んだとはいえ、国際的に見ると依然として後発です。たとえば米国では10年以上前から一人一台環境が当たり前に近づき、授業での端末活用も一般化していました。一方、日本では2020年時点で教室の無線LAN整備率が半数程度にとどまり、主要教科の授業で「デジタル機器をほとんど使わない」と答える生徒が多数を占める状況でした。
NEXT GIGAは、単なる端末更新の取り組みではなく、「遅れを取り戻し、国際水準に近づくための飛躍」としての役割が期待されています。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「令和2年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)」(文部科学省)、「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査」(文部科学省・国立教育政策研究所)を参照し、作成
電子黒板は、NEXT GIGAで掲げられる学びの進化に直結するツールです。従来の板書感覚で画面上の資料に直接書き込みができるため、教員は説明の途中で補足や図解を加え、児童生徒は視覚的に理解しやすい授業を受けられます。
さらに、インターネットと連携させれば最新のニュースなどを授業中に即座に表示でき、探究的な学びのきっかけをつくることが可能です。
動画や画像など多様な教材を瞬時に表示できる点も理解促進に有効で、端末を持つ児童生徒が自分の画面から電子黒板へ発表資料を送信し、全員で共有するような協働学習にも活かせます。
また、遠隔地の学校や海外とリアルタイムでつなぐことで、地域や国境を越えた双方向の学びを実現できるなど、学習環境の可能性を広げる役割も果たします。

電子黒板は、単なる黒板やスクリーンの代替ではなく、授業の質と学習意欲を大きく向上させる多機能な教育ツールです。ここでは、電子黒板を活用するメリットについて詳しく見ていきましょう。
電子黒板は、プリントや小さなモニターでは見づらい資料や映像を、大きな画面に表示できます。そこに教員がその場で線を引いたり、強調したい箇所を色で囲ったりすることで、説明内容を「視覚的に補強」することが可能です。
たとえば算数の図形の授業では、角度や辺を色分けして示すと、児童は目で違いを認識しやすくなります。理科の実験映像を再生しながら、化学反応の流れを矢印で示すことで、複雑な過程も直感的に理解できるでしょう。このように耳からの情報に視覚的サポートを加えることで、学習の定着度が高まります。
電子黒板をタブレットやPCと連携させれば、教員と生徒が同じ画面をリアルタイムで共有できます。たとえば国語の授業で、生徒が自分の考えを端末に入力すると、すぐに電子黒板に表示され、全員で意見を比較しながら議論できます。
また、社会科の地図資料に生徒が書き込んだ印が即座に反映されるため、その場で質問や意見交換が自然に行われます。従来の一方通行型の授業とは異なり、生徒が主体的に参加しやすい「双方向型」の授業をつくれるのが大きな強みです。
電子黒板は文字情報だけでなく、写真・グラフ・動画を組み合わせて提示できるため、生徒の興味を引きつけやすいのが特徴です。英語の授業では、単語と一緒に発音動画を流すことで発音練習がスムーズになり、美術の授業では作品画像を拡大し細部を確認することができます。
また、生徒が前に出て画面に直接書き込める機会を設けると、発言や発表のきっかけとなり、自ら学ぶ姿勢が自然に育ちます。さらに教材の切り替えもワンタッチで行えるため、授業の流れが途切れず、集中力を維持したまま効率的に学習を進めることができます。

電子黒板は一度導入すると長期的に使用するため、目的や環境に合った機種を慎重に選ぶことが重要です。ここでは、電子黒板の選び方のポイントを解説します。
電子黒板を選ぶ際は、教室全体からの視認性を確保できる画面サイズを重視する必要があります。後方の席からでもはっきり見える大きさを選びつつ、設置スペースや収納場所の条件も考慮しましょう。
タッチ操作対応のタイプであれば65〜70型が一般的ですが、広い教室ではさらに大きなサイズが効果的な場合もあります。その際、省スペースで大画面を投影できるプロジェクター型も選択肢の1つです。
電子黒板には、最新アプリを搭載し動画編集やクラウド共有まで行える多機能タイプから、板書と資料表示に特化したシンプルタイプまでさまざまな種類があります。
たとえば、理科の実験映像をリアルタイムで解析したい場合には高度なアプリ連携機能が役立ちます。また、国語の授業で板書の代替として使うだけであればシンプルなモデルでも十分でしょう。導入を検討する際は「どの教科でどのように使うのか」「生徒にどんな学習効果を期待するのか」を明確にしたうえで、それに見合った機能が搭載されているかを見極めることが大切です。
高機能な電子黒板を導入しても、操作が難しければ授業で十分に活用されない可能性があります。理想は、電源を入れてすぐに使えるシンプルな起動手順や、パソコン・タブレットとの接続が直感的に行える設計です。たとえば授業中に資料を切り替えたり、生徒の回答を表示したりする場面で、ワンタッチで操作できれば時間のロスが減り、授業のテンポも崩れません。
多機能であっても、UI(ユーザーインターフェース)が整理され、ボタンやアイコンの配置がわかりやすければ、教員が迷わず即座に使えるため、現場での利用率も高まります。
導入時や運用後のサポート体制も、機能や価格と同じくらい重視すべき要素です。例えば、授業中にトラブルが発生したときに迅速に対応してもらえるかどうかは、授業の安定性に直結します。
また、メーカーや販売代理店が研修会や操作説明会を提供していれば、教員が自信を持って電子黒板を活用できるようになり、機器が「使われないまま放置される」リスクを防げます。さらに、定期的なアップデートや修理対応の体制が整っているかを事前に確認しておくと、長期的にも安心して活用することが可能です。

電子黒板は、教科や学習テーマに合わせて多様な使い方ができる汎用性の高いツールです。地図や図形、実演映像などを大きく映し出しながら、書き込みや拡大表示で理解を深めたり、生徒の興味を引き出したりできます。ここでは、実際の授業でどのように活用されているのかを、事例を通して紹介します。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「授業がもっとよくなる電子黒板活用」(文部科学省)を参照し、作成(以下3事例)
デジタル教科書に掲載されている地図を電子黒板に大きく表示し、第一次世界大戦の背景を解説します。教師はタッチペンで特定の地域を拡大表示し、「同盟国や協商国はどのような思いで戦ったのか」を問いかけながら説明します。生徒が使用している資料を拡大して見せることで、本時のねらいや活動内容を明確に伝えられます。地理分野の地図拡大や地域比較にも応用できる活用法です。
小学4年生の国語授業では、教師が毛筆の書き方を電子黒板で拡大表示し、穂先の向きや筆運びを分かりやすく提示します。「この部分の間隔をそろえると字が整う」といった指示を加えながら、注目してほしい箇所には書き込み機能で印を付けます。毛筆だけでなく、調理実習での包丁の使い方や図画工作での彫刻刀の扱い方など、手元作業の模範提示にも応用可能です。
中学3年の数学の授業で、図形描画ソフトを使い、円周角の定理を電子黒板上で実演しました。タッチ操作で円周上の点を動かし、「角度はどう変化するか」を観察。生徒は「角度は常に同じだ」と気付きます。導入ではシミュレーションで円周角と中心角の関係を見つける動機付けを行い、続いて段階的に説明を加えながら証明の一般性を示します。操作や実験を通じて視覚的に定着を促す活用例です。
日本全国をカバーする施工・保守体制を有するバディネットは、24時間365日有人対応が可能な全3拠点のコンタクトセンターを活用し、電子黒板の導入における現地調査、設計から導入、保守、定期点検までワンストップでご提案が可能です。
電子黒板のような大型の機器の導入・保守には、本体や部品の十分な保管スペースと、サイズが大きく重量もある電子黒板を安全に運ぶ運送体制を整えていることが必要です。また、保管・運送だけでなく、エレベーターのサイズ、廊下の幅、段差などを事前に確認し、必要に応じてクレーンや特殊な搬入機材を用意するなど、納品先での専門的な搬入・設置作業における対応力も大切な要件です。
バディネットでは、これまでIT機器販売メーカー様の電子黒板の導入、保守をご支援させていただいており、これら電子黒板の導入・保守作業に必要な各種要件を整備していることはもちろん、エンドユーザー様にご説明する際に役立つトークスクリプトを含めたマニュアルの作成から運用レクチャーなどのご要望に至るまで、幅広くお応えいたします。
バディネットのデジタルサイネージ、電子黒板設置・保守に関する詳細はこちら
NEXT GIGAの時代、学校現場では端末の更新やICT活用の格差解消といった課題に直面しています。その中で活用されている電子黒板は、授業の視覚的わかりやすさを高め、双方向のやり取りや協働学習を促進するツールです。サイズや機能性、操作性、サポート体制を踏まえて適切に選定すれば、日常的な授業改善から探究的な学びの推進まで幅広く活用が可能です。
今回紹介した事例をヒントに、自校の授業や学習環境に合った導入方法を検討し、NEXT GIGAにふさわしい学びの場づくりを今から始めてみてはいかがでしょうか。
この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部
Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。