
EV充電スタンド・ステーションの導入取付設置工事・保守メンテナンス
サービス
選ばれる理由
ソリューション
企業情報
採用情報
インフォメーション
インフォメーション
「通信建設業界とバディネットを、もっとオープンに。」をテーマに
様々なコンテンツを発信


電気自動車(EV)の普及が加速する中、法人施設や商業施設でもEV充電スタンドの整備が求められるようになっています。充電スタンドを導入するには、機器の選定や設置場所の確保、補助金の申請、工事、運用体制の整備など、いくつもの工程を適切に進めることが重要です。
この記事では、EV充電スタンドの種類と設置費用、導入までの流れ、導入時に直面しやすい課題とその解決方法について解説します。

EV充電スタンドでは「普通充電器」と「急速充電器」のいずれか、あるいは両方を導入します。それぞれの特徴や導入コストを理解したうえで、使用目的や駐車時間に応じた適切な選択が求められます。ここでは、両タイプの基本性能と設置費用の目安をわかりやすく解説します。
普通充電器は、出力が比較的低く、充電に数時間を要するタイプです。一般的に集合住宅や商業施設、宿泊施設、オフィス、コインパーキングなどに設置されており、滞在時間が長めの場所に適しています。
出力は3kW、6kW、8kWなどの段階があり、広く普及しているのは3kWタイプです。3kW出力の普通充電器では、EV1台あたりの充電時間はおおよそ20時間程度が目安となります。これは、夜間や業務時間中にじっくり充電する用途に向いています。
普通充電器の設置にかかる一般的な費用は、本体費用と工事費用を合わせて40~150万円程度です。
なお、複数台設置する場合や施工条件が良い場合は、1台あたりのコストが抑えられることもあります。
急速充電器は、短時間での充電が可能な高出力タイプです。出力は25kW、50kW、90kW、150kW以上といったモデルがあり、利用シーンに応じて選定されます。
たとえば50kWの急速充電器であれば、30分程度で20kWh程度充電できます。サービスエリアや道の駅、コンビニエンスストア、自動車販売店など、短時間の立ち寄りが前提となる施設に適しています。
購入費用は1基あたり300万円以上、工事費用は約200万円以上が目安です。出力50kW超のタイプでは、高圧受電設備の追加により別途300万~600万円かかることもあります。
高出力の急速充電器は利便性が高い反面、設置コストも大きいため、補助金の活用や設置場所の精査が欠かせません。施設の導線や回転率を考慮して導入を検討するとよいでしょう。

EV充電器は「普通充電器」と「急速充電器」の2種類に分類され、それぞれ充電方式・出力・充電時間が異なります。普通充電器と急速充電器の違いについて詳しく見ていきましょう。
普通充電器は、EVが数時間にわたって駐車される場所に最適です。たとえば以下のような施設に多く導入されています。
普通充電器の設置にあたっては、3kW〜6kWの電力容量が確保できることと、分電盤との距離が近く掘削量が少ない場所であることが好ましい条件です。また、ユーザーが充電中に施設内で過ごせる環境が整っていると、満足度や再訪率の向上にもつながります。
急速充電器は、利用者の滞在時間が短く、短時間での充電ニーズが高い施設に適しています。代表的な設置先は以下のとおりです。
急速充電器の設置には、50kW以上の出力に対応できる高圧受電環境や専用の設置スペースが必要です。また、高出力によるバッテリー保護の観点から、CHAdeMO規格などとの適合確認も重要です。

企業や施設にEV充電スタンドを導入する際は、いくつかの工程を順に踏む必要があります。設置の可否を判断する現地調査から始まり、見積もり・設計、補助金の申請、そして電気・基礎工事までが一般的なフローです。
ここでは、EV充電スタンド設置までの基本的な流れをわかりやすく解説します。
最初のステップは、設置候補地における現地調査です。これは充電スタンドの設置が可能かどうかを判断するために不可欠な工程で、以下のような項目が確認されます。
この調査結果をもとに、最適な設置場所や必要な電力容量、配線ルートなどをプランニングします。建物の構造や配電盤の場所によっては、設置に向かない場合もあるため、早期の調査が重要です。
現地調査の内容を踏まえ、実際にかかる費用を算出します。見積もりには、機器本体の価格、配線工事、基礎工事、施工に関する人件費などが含まれます。あわせて、電力契約(低圧受電・高圧受電)の必要性や台数、設置レイアウトを反映した設計図も作成され、導入全体のイメージが明確になります。
EV充電スタンドの設置には、国の「充電インフラ補助金(正式名称:クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)」や地方自治体ごとの支援制度を利用することが可能です。これは、機器購入費と工事費の一部または全額が補助対象となる制度であり、企業にとって導入コストを大幅に削減できるメリットがあります。
補助金を受け取るには、所定の申請書類を揃えたうえで交付申請を行い、交付決定通知を受けてから工事に着手する必要があります。
設置位置が確定し、補助金の交付決定を受けた後は、現地での工事に進みます。まず行われるのが基礎工事で、EV充電器を設置するための土台をつくる作業です。具体的には以下のような工程が含まれます。
充電器がしっかりと安定して稼働するために、基礎工事の精度は重要です。
基礎が完成したら、次に電源および配線工事が行われます。この工程では、既存の分電盤やキュービクルなどから電力を引き込み、充電器までのケーブル敷設を行います。
電気系統と安全基準に基づいた適切な施工が求められるため、信頼できる専門業者の手配が不可欠です。完了後は、試運転と安全確認を経て、運用開始となります。

EV充電スタンドの導入は、企業や施設にとって環境配慮や顧客サービス向上に寄与する一方で、初期投資や運用面においていくつかの課題も発生します。
ここでは、導入に際してよく挙げられる3つの課題と、それに対する具体的な対策について解説します。
EV充電スタンドの運用では、機器の導入費用や設置工事費に加えて、日常的な電気料金の負担が企業にとって大きなコストになることがあります。特に急速充電器のように高出力な設備を導入した場合や、充電需要の多い施設では、月々の電力使用量が増加し、運用コストが膨らむ懸念があります。
このような状況に対しては、まず「充電インフラ補助金」などの公的支援制度を活用することで、導入時の金銭的な負担を大きく軽減することが可能です。
さらに、スマート充電に対応した機器を導入すれば、電気代の高い時間帯を避けて充電を行う「ピークシフト充電」や、稼働状況に応じた電力の最適化が可能となり、電力コストを継続的に抑えることができます。
また、従量課金方式によって利用者から充電料金を徴収する仕組みを導入すれば、ランニングコストの一部を収益化することも可能です。
充電スタンドを設置したいと考えていても、駐車場が狭かったり、建物の構造上レイアウトが限られていたりして、設置に踏み切れないといった相談は少なくありません。しかし、スペースの問題は必ずしも導入を諦める理由にはなりません。
現地調査を通じて設置条件を丁寧に確認すれば、条件に合った機器構成や設置工法によって対応できるケースは多く存在します。
バディネットでは、こうしたスペース条件の制約に対応したレイアウト設計や、最適な配線計画の立案、各種機器の選定サポートまでを含めた提案を行っています。導入を諦める前に、ぜひ専門家による現地調査と提案を受けてみてください。
EV充電スタンドは屋外に設置されることが多く、雨風や気温変化などの自然環境にさらされるため、導入後も安定して稼働させるためには定期的な保守点検が必要です。
たとえば、外装の劣化や破損の有無、端子や配線のゆるみ、充電性能の確認、課金システムの動作チェックなど、多岐にわたる点検作業が定期的に求められます。これらを怠ると、予期せぬ機器トラブルが発生し、利用者の信頼を損ねるだけでなく、施設側の負担や収益機会の損失にもつながりかねません。
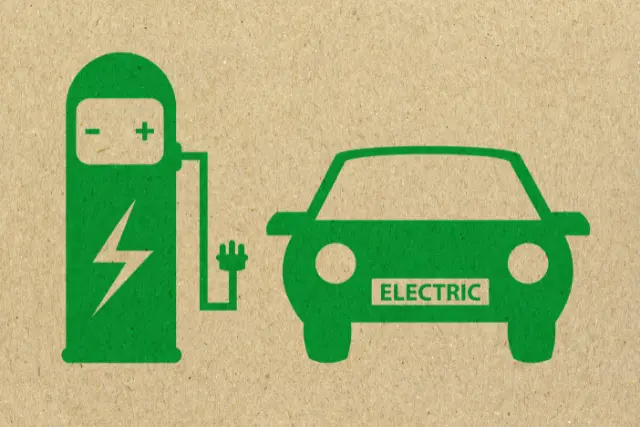
日本全国をカバーする施工・保守体制を有するバディネットには、EV充電スタンドの導入工事に必要な専門知識と各種資格を有したスタッフが多数在籍しており、全国を対象として調査・設計から補助金申請業務、電力各社への申請対応や関連法規に基づく手続き、施工、アフターフォローまでをワンストップでご提案が可能です。
また、集合住宅への導入に際しては、マンションオーナー様や管理組合様に向けたご提案やご要望に応じた交渉支援などにも柔軟に対応しております。
バディネットのEV充電スタンド導入・保守に関する詳細はこちら
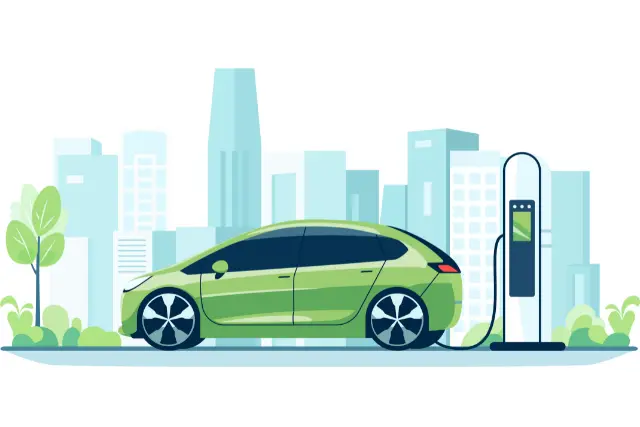
EV充電スタンドの導入には、設置環境や目的に応じた機器の選定と、補助金制度の活用、そして現地調査から設置工事・保守体制の整備に至るまで、計画的な進行が求められます。普通充電器と急速充電器では導入費用や利用シーンが異なるため、施設の用途や利用者層を踏まえた選定が不可欠です。また、電気代の負担、設置スペースの確保、導入後のメンテナンスといった課題も、事前の準備と専門業者のサポートにより的確に対応できます。
バディネットでは、補助金申請や電力会社との調整、設計・施工、保守対応までワンストップで支援しています。EV充電設備の導入をご検討中のメーカー・サービスベンダー様は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部
Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。