
データセンターの必要性や将来性、選ぶ際のポイントについて解説!

デジタル社会の進展に伴い、膨大なデータを効率的に処理・保管するためのインフラ整備が急務となっています。従来のビル型データセンターは、大規模な用地や建設期間を必要とすることから、柔軟性に乏しいという課題を抱えていました。こうした背景の中で、注目を集めているのが「コンテナ型データセンター」です。
この記事では、コンテナ型データセンターの概要やメリットに加え、導入に向けた課題や法的な留意点、実際の活用事例までを詳しく解説します。
目次

コンテナ型データセンターとは、ITインフラの中核をなすサーバーや冷却装置、電源装置、セキュリティシステムなどを、ひとつの輸送用コンテナにまとめて収容した可搬型のデータセンターを指します。
従来の建物型データセンターとは異なり、あらかじめ機器を組み込んだ状態で出荷されるため、導入先に到着すればすぐに稼働できるのが特徴です。
2000年代後半、クラウドサービスの拡大とともにアメリカのIT企業を中心に登場しました。設備投資を抑えつつスピーディーに拠点展開できることから、研究機関や災害対応拠点、仮設インフラなどで活用が進みました。日本国内でも災害時のBCP(事業継続計画)対策として注目され、近年では生成AIやエッジコンピューティングの普及により、再び脚光を浴びています。
データセンターの必要性や将来性、選ぶ際のポイントについて解説!

コンテナ型データセンターが注目されている背景には、デジタル化の加速と従来型施設の限界があります。近年は、DXの推進や生成AIの活用により、処理すべきデータ量が急増しています。一方で、従来のデータセンターは建設に時間がかかり、用地や電力の確保が難しいケースも少なくありません。こうした課題を解決する手段として、短期間で導入できるコンテナ型が注目されています。
また、東日本大震災以降、企業の間ではBCP(事業継続計画)に対する意識が高まりました。災害や障害の発生時にも、事業を止めずに運用を継続できる体制づくりが求められており、可搬性や柔軟性に優れたコンテナ型は、バックアップ拠点としても有効とされています。このようなニーズに対応できる点が、多くの企業から支持を集める理由です。
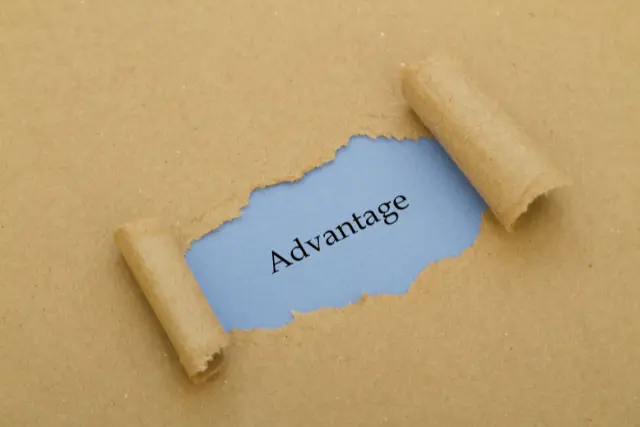
コンテナ型データセンターは、従来のビル型施設と比べて短期間での構築が可能で、初期費用や運用コストも抑えられます。あらかじめ機器を組み込んだ状態で出荷されるため設置が容易で、スペースに制限のある場所にも柔軟に対応できます。また、将来的な拡張にも対応しやすい点も強みです。
コンテナ型データセンター建設のメリットについて詳しく見ていきましょう。
コンテナ型データセンターは、従来のように専用の建物を最初から建設する必要がなく、スピーディーに導入できる点が大きな特長です。一般的なデータセンターは完成までに数年を要しますが、コンテナ型であれば数か月という短期間で稼働を開始できます。
これは、あらかじめ工場で機器の組み込みやテストが完了した状態で出荷されるためです。現地では、設置・接続といった最小限の作業だけで運用を始められるため、新拠点の立ち上げやBCP対応にも柔軟に活用できます。
コンテナ型データセンターは、建物の建設や内部構築にかかる大規模な投資を必要とせず、導入コストを大幅に抑えられます。メーカー側で主要な機器や配線があらかじめ組み込まれているため、現地での作業が少なく、設置にかかる人件費や工期の削減にもつながります。また、専用の土地を取得・整備する必要がない点も、固定資産コストの軽減に貢献します。
さらに、運用面では高密度な機器配置と効率的な冷却設計によって、消費電力を抑える工夫がなされています。自然空調や再生可能エネルギーの活用、高電圧直流給電などの技術も導入されており、ランニングコストの最適化に寄与します。保守運用の効率化によって人的コストも削減でき、トータルで見てもコストパフォーマンスに優れた選択肢といえます。
コンテナ型データセンターは、設置場所に対する柔軟性の高さが大きな強みです。従来のようなビル型データセンターでは、広大な土地や堅牢な建物が必要でしたが、コンテナ型であればその制約を受けません。基礎工事を最小限に抑えられる構造のため、既存施設の敷地内や倉庫、屋上、駐車場といったスペースにも無理なく導入できます。
特に都市部では、用地取得や建設にかかるコスト・時間が課題となる中で、限られたスペースを有効活用できるコンテナ型は、インフラ整備の新たな選択肢として注目されています。
ビジネスの成長やサービスの拡充に伴い、データセンターの処理能力やストレージ容量を増やす必要が生じることがあります。コンテナ型データセンターは、こうしたニーズに応える柔軟な拡張性を備えています。
モジュール化された構造により、既存設備に追加のコンテナを接続するだけで、スムーズにキャパシティを増強できます。従来のビル型施設のように、大がかりな増築工事を行う必要はなく、運用中のシステムに大きな影響を与えることもありません。変化の速い時代において、スピーディーかつ効率的に拡張できる点は、大きなメリットといえるでしょう。

コンテナ型データセンターは、短期間で導入できることやコスト削減といった多くの利点がありますが、導入時に考慮すべき課題も存在します。特に、日本のように自然災害が多い国では、設置場所やセキュリティへの配慮が欠かせません。また、構造上の制限から、電力や冷却性能、処理能力の面で制約が生じるケースもあります。
ここでは、コンテナ型データセンター建設における課題について解説します。
コンテナ型データセンターは可搬性に優れている一方で、屋外設置が基本となるため、物理的なセキュリティ対策に注意が必要です。日本のように地震や台風、津波といった自然災害が多い地域では、設置場所の選定が重要な要素となります。
また、建物型に比べて構造が簡易であることから、外部からの侵入リスクも相対的に高くなります。不正侵入や破壊行為によってデータセンターが停止するリスクを想定し、監視カメラや入退室管理システムなど、物理的な防御策の強化が求められます。
コンテナ型は限られた空間に設備を収める必要があるため、電力供給や冷却機構に制約が生じやすいという課題があります。とくに、AI処理などを行うGPUサーバーは一般的なサーバーに比べて発熱量が大きく、冷却性能への要求も高まります。冷却が十分でなければ、機器の安定稼働に支障が出るおそれもあります。また、電力消費も年々増加しており、コンテナ型の限られた設置面積のなかで、いかに効率的な電力設計を行うかがポイントです。
コンテナ型データセンターは、必要な機器をひとつにまとめたコンパクトな構成が魅力ですが、大規模な計算リソースを求められる用途には向かない場合もあります。特に、AIのトレーニングや大規模なクラウドインフラのように、高度なコンピューティング性能を要求されるシーンでは、一般的なビル型データセンターに比べて性能が制限されることがあります。
用途に応じた設計や配置が必要となり、万能ではない点を理解して導入を検討することが大切です。

コンテナ型データセンターを導入する際は、法律も考慮しなくてはなりません。特に気を付けなくてはならないのは、消防法と建築基準法の2つです。では、実際にどのような点に注意するべきなのか、詳しく見ていきましょう。
コンテナ型データセンターを導入する際には、消防法上の取扱いについても十分な配慮が必要です。消防庁が平成23年に示した指針によると、一般的なサイズ(おおよそ30㎡)のコンテナを単体で使用する場合、多くのケースで消防用設備の設置義務は発生しないとされています。
ただし、複数のコンテナを連結・積層して使用する場合や、合計の床面積が一定の基準を超える場合には、「防火対象物」として消防用設備の設置が求められる可能性があります。たとえば、自動火災報知設備や消火器、スプリンクラー設備などが必要となるケースも想定されます。
導入時には、運用規模や設計内容に応じて、地域の消防署や関係機関と事前に協議し、法令に適合した設備設計を行うことが重要です。初期段階から法規制を考慮することで、安全かつスムーズな運用体制を構築しやすくなります。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「コンテナ型データセンターに係る消防法令上の取扱いについて」(消防庁)を参照し、作成
コンテナ型データセンターは、建築基準法の観点からも特有の扱いがなされており、設置にかかる手続きの簡素化につながる場合があります。国土交通省は平成23年、稼働時に人が常駐せず、最低限の設備と空間のみを有するコンテナ型データセンターについて、一定の条件を満たす場合は建築物に該当しないとの見解を示しました。
具体的には、土地に自立して設置され、通常は内部に人が立ち入らない仕様であれば、「貯蔵槽その他これらに類する施設」として分類され、建築確認などの手続きが不要になるケースがあります。
ただし、コンテナを複数積み重ねる場合や、人が常時立ち入るような構造であれば、建築物として取り扱われる可能性があるため、設計段階での法令確認が欠かせません。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて」(消防庁)を参照し、作成
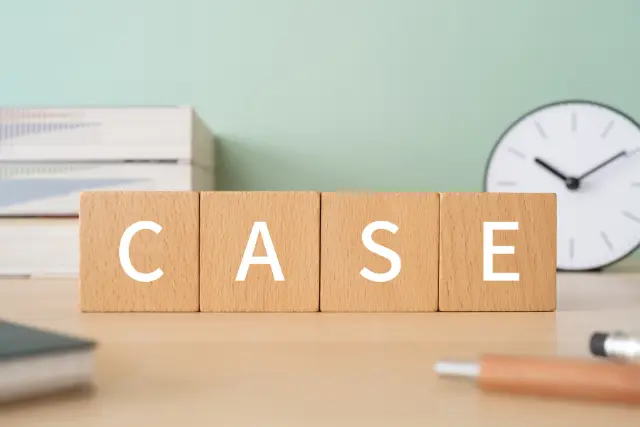
コンテナ型データセンターは、可搬性や短納期といった特性を活かし、多様な現場での活用が進められています。どのように活用できるのかを知ることで、導入後のイメージもわきやすいでしょう。ここでは、コンテナ型データセンターの活用事例を紹介します。
近年、コンテナ型データセンターはその高い柔軟性と迅速な導入性から、多様な分野での活用が進んでいます。中でも注目されているのが、再生可能エネルギーと組み合わせた運用モデルです。
例えば、太陽光発電や蓄電池を活用して自家消費型のエネルギー運用を行うコンテナ型データセンターの導入が、再エネポテンシャルの高い地域で拡大しています。既存の敷地や物流施設の屋根面を利用して太陽光パネルを設置し、発電した電力をそのままデータセンターで使用する取り組みも見られ、再エネ×データセンターという新たな地域エネルギーモデルとして注目が集まっています。
また、蓄電池を併用することで、再エネ比率の向上と同時に、非常時のバックアップ電源としての機能も担っています。とくに電力供給が不安定な地域や、BCP対策を重視する企業にとっては、分散型かつ可搬型のデータインフラとして非常に高い価値を持ちます。
こうした活用は民間企業だけでなく、政府や自治体レベルでも導入検討が進められています。
たとえば、富山県では「地方創生型次世代データセンター構想モデル」として、水力発電とコンテナ型データセンターを組み合わせた地域経済活性化の取り組みが提唱されています。災害リスクが低く、豊富な自然エネルギー資源を持つ地域にデータセンターを分散配置することで、AI時代に対応したインフラ整備と地域産業の育成を同時に進める構想です。
このように、再エネ活用や地方分散を前提としたデータセンター構築において、コンテナ型という形式が持つ機動力と省スペース性は、非常に親和性が高く、今後のデジタル社会を支えるインフラとしてさらに需要が高まると考えられます。
※Buddy Net CONNECT編集部にて、「データセンターによる再エネ利活用優良事例集(R3~R6)」(環境省)、「地方創生型次世代データセンター構想モデル富山」(自民党県連TOYAMA)を参照し、作成
バディネットは、日本全国をカバーする施工・保守体制を有し、電気・電気通信建設工事を中心とした社会インフラ構築工事業を幅広く展開しています。ハードウェア関連事業を展開するグループ会社のアドテックと連携することで、コンテナ型データセンターの設計、部材の調達をはじめ、施工から運用・保守まで一気通貫で対応が可能です。
経験豊富な技術力のあるエンジニアが、お客様のご要望にあったコンテナやコンテナ内部のIT機器の選定から、電力供給や冷却システムなどのインフラ整備をはじめ、コンテナへの機器搭載や配線工事、運用開始前の検証、運用後の保守メンテナンスなどを担当しており、高品質な施工、アフターサポートを実現いたします。

コンテナ型データセンターは、迅速な導入やコスト削減、設置場所の柔軟性、将来的な拡張性など、従来型施設にはない多くのメリットを持ちます。
一方で、物理的セキュリティや冷却効率、法規制への対応といった課題にも注意が必要です。
再生可能エネルギーとの組み合わせや地方分散型モデルの展開など、活用の幅も年々広がっており、今後のデジタル基盤としてますます期待が高まっています。持続可能かつ強靭なITインフラを構築するうえで、コンテナ型データセンターは選択肢の1つといえるでしょう。
この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部
Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。